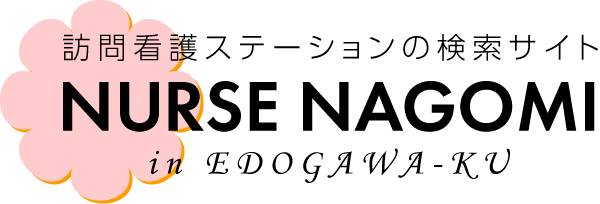このページでは訪問看護ステーションの求人情報を探す方向けに、江戸川区内で訪問看護ステーションを選ぶ際の具体的なポイントを説明しています。
1. 教育・研修制度
未経験者やブランクがある場合は特に重要なポイントです。そして、一人で訪問することになるため、スタッフ間のサポートも重要になります。
確認すべき具体的な項目:
- 新人研修の具体的な内容(同行訪問の回数・期間など)
- 職場内のカンファレンスは充実しているか
- 担当制かどうか。一人の利用者に対し複数のスタッフが交代で訪問するのか?
- 外部研修や学会への参加が奨励されているか
- 認定看護師などの資格取得の費用補助や勉強のサポートがあるか
2. 働きやすさや職場の雰囲気
職場の雰囲気が良いと、安心して働けますが、入職前に把握することはなかなか難しいかもしれません。できれば、見学として一日でも訪問同行させてもらうと良いでしょう。
確認すべき具体的な項目:
- スタッフの年齢層や男女比、職種(リハビリ職が多い場合もあります)
- 現場でのコミュニケーション(チーム内の協力体制)
- 上司や管理者との関係性(相談のしやすさ)
- 離職率や勤続年数、退職の理由
3. 訪問エリアと移動手段
日々の移動は負担に直結するため、無理のない範囲かを確認しましょう。訪問看護では、自転車の場合、雨天の際の移動は雨具を着ますが、各々快適に移動できるよう工夫しています。江戸川区の場合、ほとんどが坂が少ない平地という有難い特徴があります。
確認すべき具体的な項目:
- 訪問エリアの範囲(事業所から近いかどうか)
- 1日の平均訪問件数と移動時間(件数が少なくても移動時間が多いと大変です)
- 移動手段(車、自転車は電動か、雪の日の移動など)
- 駐車場や交通費の支給状況
4. オンコール体制
オンコールの対応頻度や体制は負担感に大きく影響します。訪問看護ステーションとしては、できるだけ夜間にコールが無いよう、訪問時などに対応しておく必要があります。ご利用者にとっては、24時間連絡が取れることで安心感につながります。
確認すべき具体的な項目:
- オンコールの頻度(月に何回程度か、連日の場合何日までか)
- 夜間や緊急時の対応マニュアルが整備されているか
- 入職後のオンコールの開始時期やサポート体制はどのようになっているか
- オンコール手当の金額や支給条件
- オンコールで夜間に呼ばれた時の翌日の勤務体制(時間給など取得可能か)
5. 給与や福利厚生
安定して働き続けるためには、待遇面も重要です。ただ、訪問件数によって賞与などは変動することがあります。また、訪問1件当たりの訪問単価=給与ではなく、様々な経費も掛かっていることも念頭に置きましょう。
確認すべき具体的な項目:
- 短時間勤務の有無とそのシフトについて
- 基本給とインセンティブの仕組み(訪問件数連動型か固定型か)
- 賞与や昇給の実績
- 有給休暇や育児時間の取得率や取りやすさ
6. ご利用者の特徴
自身の臨床経験を踏まえ、自分の経験を活かせる職場かどうかを確認しましょう。幅広い対象であっても、スタッフの人数が多ければ、自身の経験を活かせる分野のご利用者を担当できる場合もあります。江戸川区の地域の特徴として、北側半分の高齢化率が高くなっており、戸建てが多く、家族で住んでいる割合が多いと感じます。
確認すべき具体的な項目:
- 年齢層(小児~高齢者まで幅広いか特定の層か)
- 診療内容(ターミナルケア、精神科、難病患者など)
- 医療保険と介護保険の割合(訪問看護ステーションによって異なります)
7. ICT(情報通信技術)の活用状況
最近では訪問看護ステーションでも業務ソフトを活用した電子カルテも導入されていることが多くなっています。ICTの活用で効率的な働き方が可能になります。
確認すべき具体的な項目:
- 記録システムやタブレットの導入状況。
- 情報共有の手段(LINE、専用アプリなど)。
- 業務中や訪問の空き時間に記録の入力が可能か。
8. その他のポイント
江戸川区の特徴として、介護保険制度開始時期からある訪問看護ステーションと、開設して10年未満のステーションに2分されている傾向があります。そのため、ベテランの訪問看護師から多くのことを学べる機会も多いと思います。
また、ステーションの理念はどの訪問看護ステーションにもありますが、目指している方向性と実際が合っているかについて、確認も必要かと思います。
以上のポイントを参考に、自分のスキルを発揮でき、働きやすいと感じられる環境をしっかり見極めることが重要です!
検索ページで、それぞれの訪問看護ステーションの特徴を比較して、あなたにピッタリの訪問看護ステーションを見つけてください!
訪問看護ステーションを探す!
グループリンクまた、訪問看護ステーションに直接問い合わせしにくい場合は、ウェブサイトのお問い合わせページから葉山までお問い合わせいただいても構いません。